介護保険サービスの利用者の負担について
介護保険のサービスを利用した場合、かかった費用の1割から3割(3割は平成30年8月から)を事業者に支払います。各負担割合の対象となる人は次の通りです。
負担割合 3割
次の1,2の両方に該当する場合
- 本人の合計所得金額が220万円以上
- 同一世帯にいる65歳以上の人の[年金収入+その他の合計所得金額]が、単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上
負担割合 2割
3割に該当しない人で、次の1,2の両方に該当する場合
- 本人の合計所得金額が160万円以上
- 同一世帯にいる65歳以上の人の[年金収入+その他の合計所得金額]が、単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上
負担割合 1割
上記以外の人
介護保険で利用できる額には上限があります
主な在宅サービスは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用するときは、サービス費用の負担割合分の費用で利用できますが、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額利用者の負担となります。
利用者負担が高額になったとき
同じ月に利用した介護保険のサービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)して、上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。
| 利用者負担段階区分 | 上限額(月額) | |
|---|---|---|
| 住民税課税世帯で課税所得690万円以上 | 世帯140,100円 | |
| 住民税課税世帯で課税所得380万円から課税所得690万円未満 | 世帯 93,000円 | |
| 住民税課税世帯で課税所得380万円未満 | 世帯 44,400円 | |
| 住民税非課税世帯 | 世帯 24,600円 | |
| 住民税非課税世帯で ・老齢福祉年金の受給者 ・合計所得金額および課税年金額の合計が80.9万円以下の人 |
世帯 24,600円 個人 15,000円 |
|
| 生活保護の受給者 | 個人 15,000円 | |
| 利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合 | 世帯 15,000円 | |
施設サービスの費用
施設サービスを利用した場合には、サービス費の自己負担分(1~3割)に加えて、食費、居住費、日常生活費を施設に支払います。
居住費・食費の基準額
利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、居住費・食費の平均的な費用を参考に定められた額(基準費用額)が定められています。
基準費用額(1日あたり)
|
居住費等 |
食費 |
|||
|
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 |
多床室 |
|
|
2,066円 |
1,728円 |
1,728円 (1,231円) |
437円 (915円) |
1,445円 |
(注意)・()内は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合
・2型介護医療院などの一部の多床室において、室料が徴収されます。
低所得の人には負担限度額が設けられています
低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により、一定額以上は保険給付されます。所得に応じた負担限度額までを負担し(1から3段階2)、残りの基準費用額との差額分が給付されます(特定入所者介護サービス費等)。
|
利用者負担段階区分 |
居住費等 |
食費 |
|||||
|
ユニット型個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 |
多床室 |
施設 サービス |
短期入所 サービス |
||
|
第1段階 |
〇本人および世帯全員が住民税非課税世帯で、老齢福祉年金の受給者 〇生活保護の受給者 |
880円 |
550円 |
550円(380円) |
0円 |
300円 |
300円 |
|
第2段階 |
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80.9万円以下の人 |
880円 |
550円 |
550円(480円) |
430円 |
390円 |
600円 |
|
第3段階(1) |
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80.9万円超120万円以下の人
|
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 |
650円 |
1,000円 |
|
第3段階(2) |
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人
|
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 |
1,360円 |
1,300円 |
(注意)()内は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合
(注意)次のA、Bのいずれかに該当する場合は、対象となりません。
A:住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税の場合
B:住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も住民税非課税)でも、預貯金等が一定額を超える場合
- 第1段階 :預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
- 第2段階 :預貯金などが単身 650万円、夫婦1,650万円を超える場合
- 第3段階(1):預貯金などが単身 550万円、夫婦1,550万円を超える場合
- 第3段階(2):預貯金などが単身 500万円、夫婦1,500万円を超える場合
申請に必要なもの
【記入例】負担限度額認定申請書 (PDFファイル: 152.6KB)
負担限度額認定申請のチェックリスト※申請前にご確認ください。 (Wordファイル: 12.1KB)
- 預貯金(普通・定期)・・・通帳の写し(銀行名・支店名・名義・最終残高の分かるところ)最新の状態で直近2ヵ月分
- 有価証券・投資信託・・・証券会社や信託銀行の口座名義等と残高記載箇所の写し(ウェブサイトの写しも可)
- 負債(借入金・住宅ローン等)・・・借用書の写し
- 金・銀(積立購入含む)など購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属・投資信託など)について、複数保有している場合は、そのすべての写し
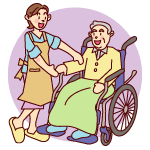














更新日:2025年08月13日